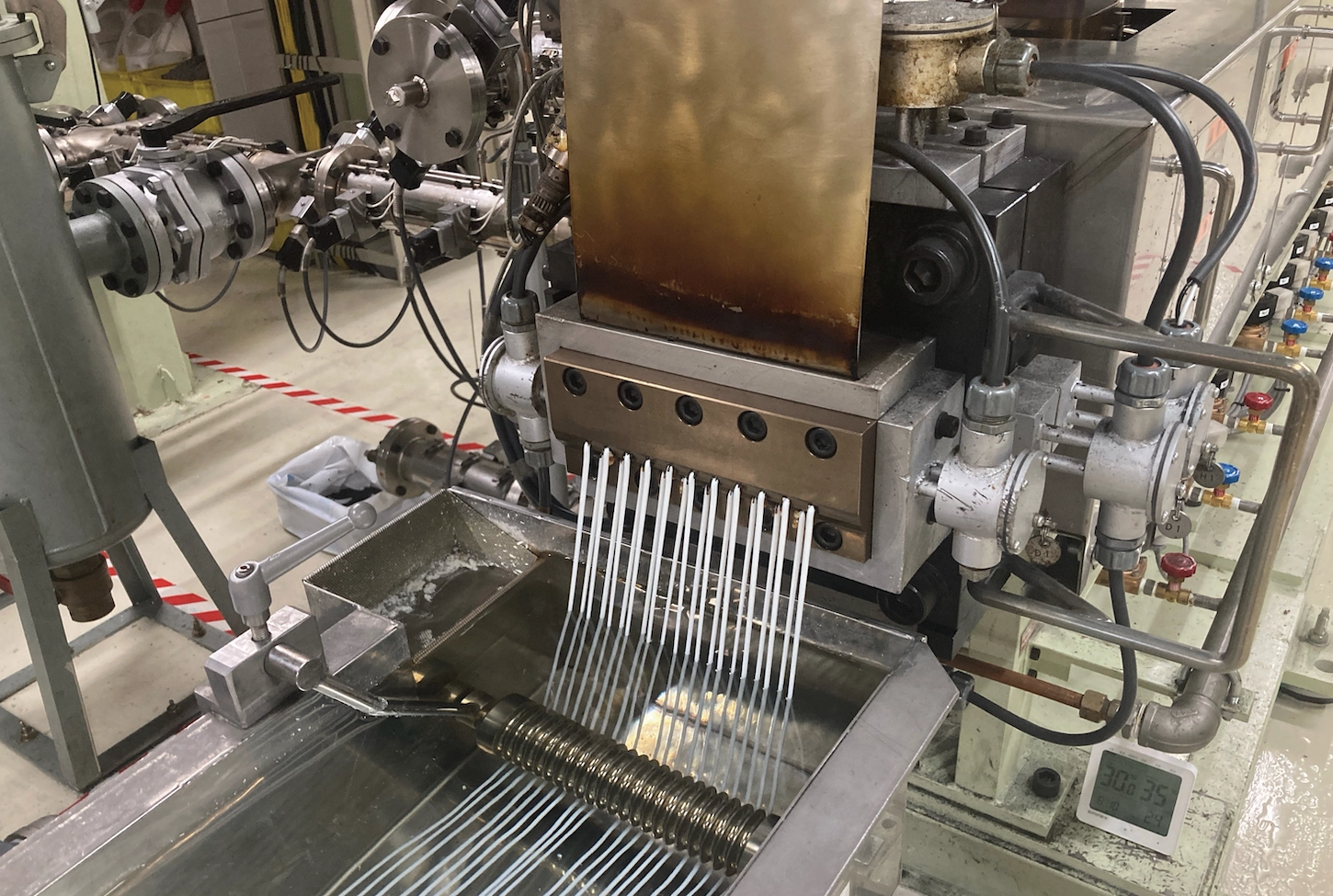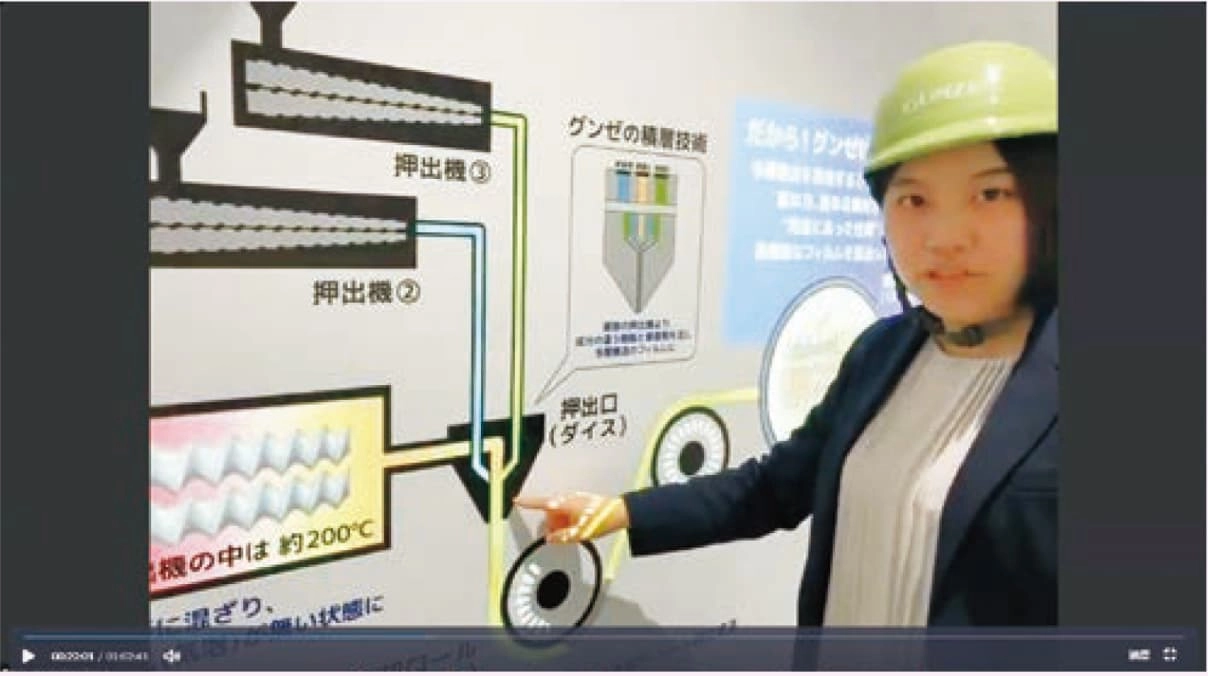グンゼは、プラスチックの3R + Renewable※を積極的に推進し、廃棄量を削減することで、
プラスチック資源が循環する社会の実現に貢献する。
- プラスチックの減量化・再利用を推進する。
- 分別・リサイクルし易い製品設計と再生原料の積極的使用により、効果的・効率的なプラスチック資源循環に貢献する。
- 植物由来原料による製品開発を行い、石油化学原料の使用量削減に貢献する。
- 廃棄物の適切な管理と環境負荷を低減する生産活動により、つくる責任を果たす。
-
※3R + Renewable
3Rは、Reduce(リデュース=製品をつくる時に使う資源の量を少なくすることや廃棄物の発生を少なくすること)、Reuse(リユース=使用済製品やその部品等を繰り返し使用すること)、Recycle(リサイクル=廃棄物等を原材料やエネルギー源として有効利用すること)の頭文字 R を指し、これにRenewable(リニューアブル=再生利用)を加えたもの。